セルフストレッチの方法
1 姿勢:背もたれのない椅子坐位、もしくは立位。
2 方法:息を吐きながら動かす。十分に動かした最後の姿勢を3秒間保持する。
3-1 腸肋筋:上半身を回旋する。脊柱全体の問題なので、腰部を回旋しよう、
肩甲間部を回旋しよう、という様に意識を集中して行う。片側3回程度。
3-2 棘筋、最長筋、半棘筋:体前屈、上記と同様である。
3-3 最長筋:体側屈
3-4 多裂筋:上半身を大きく回す。
上記の運動はどれもラジオ体操で行われている体操である。
深層背筋は、上・下肢の運動に直接関わらない、
上・下肢の発生する以前からの筋群とも考えられる筋群です。
生命維持に関わりの大きい筋群であることが考えられます。
2008年にNHK総合テレビでラジオ体操は、「体力的効果は望めない」という放送がなされました。
覚えておいでの方も多いと思います。
「命に関わる機能が高まる」のだというのが、2008年10月22日のためしてガッテンの放送でした。
私は、深層背筋のセルフストレッチをしてみました。やってみてびっくりしました。
セルフストレッチで行うことになる運動が、ラジオ体操の中に全部あったのです。
「命に関わる機能が高まる」というのは、思いがけなくバランスを乱すような場面に直面したときの身のこなしが良くなるということでした。
それは脳のイメージの問題と説明していましたが、深層背筋の機能を高めると考えるとそれでも説明が可能です。
ラジオ体操は、リズム運動です。拮抗筋抑制というメカニズムで筋の過緊張が解けやすくなります。
セルフストレッチをするとさらに深層背筋の疲労が解けやすくなります。
ラジオ体操をして、セルフストレッチをするというのが理想的です。
来週、深層背筋のセルフストレッチの方法を書きます。
3月6日に「9割の病気は自分で治せる」岡本 裕著、中経出版 を紹介しました。
日本の医療の現状を医師として反省し医療を見つめています。
高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満症、痛風、便秘症、頭痛、腰痛症、不眠症、
自律神経失調症などの慢性疾患は、薬物は対症療法であり症状を軽減するのみで根治療法ではない。
むしろ身体の治す力を弱くしてしまい治りにくくする。
生活習慣を改善し身体がもつ自然治癒力を生かすことこそ医療の根本治療と叫んでいます。
患者自身が自分自身の人生と向き合い薬に依存しない自立的な生活が医療の基本です。
鍼灸などの治療も依存性を与えるのではなく、
患者が生活習慣を改善し症状を改善して行く介助役としてあるべきです。
身体がもつ自然治癒力を主とする治療は、介助役として最も推奨されます。
鍼灸師は、患者に本当に望ましい治療を提供しているのです。
自信を持って患者に伝えて行かなければなりません。
そのことが患者の本当の指示を受けられることです。
患者を変え、社会を変えます。鍼灸師の仕事に対する本当の自信が日本の将来を明るくします。
鍼灸師の将来を明るくします。
6 30分で行う鍼治療の仕組みの基本的考え方
① 治療を構成する三つの条件を満たし、削ることのできるものを削る。
② 仰臥・伏臥位の治療で置鍼、パルス治療の刺鍼を先に行う。
6-1 腰痛鍼治療:立位バランスを整える
① 浅刺・呼気時・坐位の刺鍼 7呼吸回 1寸 02番 1本
② 腹部刺鍼 未病の徴 寸3 02番 10本
③-1 腰部局所刺鍼 10分間置鍼
大腰筋 2寸 3番 2本
中殿筋 2寸 3番 2本
足底筋 1寸 02番 2本
③-2 背部刺鍼 未病の徴 寸3 1番 10本
④ 浅刺・呼気時・坐位の刺鍼 10呼吸回 1寸 02番 1本
6-2 肩こり・緊張型頭痛の鍼治療
① 浅刺・呼気時・坐位の刺鍼 7呼吸回 1寸 02番 1本
② 背部刺鍼 未病の徴 寸3 1番 10本
肩外兪、肩中兪、天りょうの部、肩甲間部、に3本
Th7以下の背中に2本
③ 側臥位での頸部治療 寸3 02番 6本
天柱・風池・Cの4もしくは5の外側。3本
④-1 M6 10分 寸3 3番 4本
④-2 腹部刺鍼 未病の徴 寸3 02番 10本
⑤ 浅刺・呼気時・坐位の刺鍼 10呼吸回 1寸 02番 1本
6-3 疲労回復の鍼治療
① 浅刺・呼気時・坐位の刺鍼 7呼吸回 1寸 02番 1本
②-1 腰部局所刺鍼 10分間置鍼
大腰筋 2寸 3番 2本
足底筋 1寸 02番 2本
②-2 背部刺鍼 未病の徴 寸3 1番 10本
③ 側臥位 頸部刺鍼 寸3 02番 6本
④-1 M6 10分 寸3 3番 4本
④-2 腹部刺鍼 未病の徴 寸3 02番 10本
⑤ 浅刺・呼気時・坐位の刺鍼 10呼吸回 1寸 02番 1本
鍼基礎・臨床実習:刺鍼の基本的実習から臨床基礎実習へ⑩ で一応のまとめとします。
前回のものに解説が必要かと思います。次週に行います。
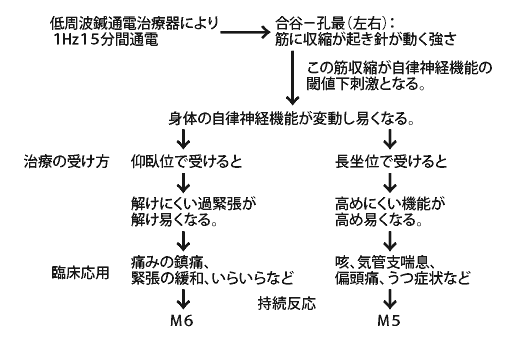
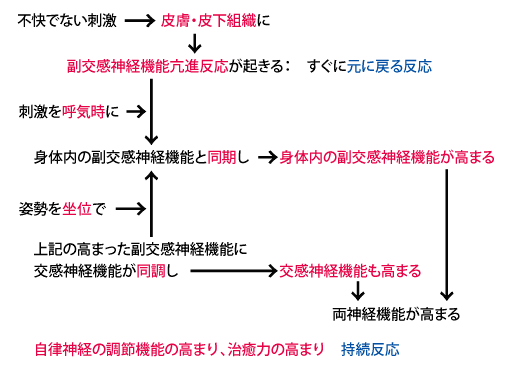
新着記事一覧
(05/27)「社会的孤独」
(05/05)[ 「2021年」聖徳太子、没後1,400年
(02/29)土曜の一言を復活させなければならない責任を感じました
(02/12)「”上を向いて歩こう”全米NO.1の衝撃」
(03/14)美味しいご飯の炊き方
QRコード


